中学生は「反抗期」と真っ只中の齢で、思春期も相まって難しい年代といわれています。友人関係や進学への悩みを抱え、精神的にも不安定な時期です。そんな生徒と向き合う中学校教師は、授業だけでなく、他にもいろいろな仕事を抱えています。その他の仕事の内容とは、どのようなものでしょうか。
中学校教師の仕事について
中学校教師の仕事内容
- 中学校教師の本分は教科指導
- 部活動指導も仕事のひとつ
- 生徒指導も大切な仕事
中学校教師の代表的な仕事は、教科指導です。小学校の教師はほとんどの教科を一人の教師が教えますが、中学校は教師が専門の科目を教えます。担任を持つ先生もいますが、授業を受け持つのは自分のクラスだけではなく、学年ごとに教えるという場合がほとんどです。クラスによって授業の進み方が違ってしまわないように、同じように授業を進めていく裁量が必要です。
また、1年を通してどのように授業を進めていくのか、スケジュールを立ててそれに乗っ取り授業をします。小テストや中間テスト、期末テストで生徒たちの理解度を把握し、夏休みなどは補修や受験に向けた対策授業を行います。高校受験を控えた中学3年生を教える場合は、高校受験を意識した内容で取り組むということもあります。いかに分かりやすい授業を行うかが、中学教師の課題です。
中学校の部活動の目標は、積極性や協調性を学び、目標を達成するために努力することや、達成した時に充実感を学ぶというものです。中学生にとって、部活動とは学校生活の中で大きな比重を占めています。クラス以外の仲間と過ごす3年間という期間は、人生の中でも強い印象を残し、生涯の思い出となります。その思い出をいいものにするかどうかは本人はもとより、教師の力量にもかかってくるのではないでしょうか。
生徒と共に一つの目標を目指して取り組み、生徒たちの様子を観察して叱咤激励して生徒の気持ちに寄り添いながら授業とは違ったところで、生徒との時間を過ごします。放課後や休日という長い時間を一緒に過ごすことで強い絆が生まれ、生徒たちが充実した部活動の時間を過ごせるよう見守ることは、中学校教師の大切な仕事です。
生徒指導とは、問題を起こした生徒を指導することではなく、生徒個人の人格を尊重してその個性を伸ばし、学校生活の中で社会的な資質や行動力を高めるように指導することです。中学校教師は学級担任や担当授業を通し、生徒たちの様子を観察して悩みやトラブルを抱えていないか気づくことが必要です。
中学生は思春期の最中で、精神的に不安定になることがあります。クラスの中や部活動の仲間との関わり、親との関係に悩みを抱える生徒もいることでしょう。教師はそんな生徒たちの相談相手になり、中学生活を支えていく役割もあります。

中学校教師の年収はどのくらい?
中学校教師の平均月収は、約45万円ほどです。初任給は大学卒業で約24万円となっていて、教師は年齢が上がるにつれて上がるのですが、教師の仕事は授業だけでなく、放課後の部活動や土日の部活動への参加などがあることが多いです。
文化祭や体育祭の準備、テスト前の準備などで残業をすることもあります。修学旅行では夜もゆっくり寝ていられないような忙しい仕事です。この収入がその仕事に比例しているかどうか考えると、そう高収入とは言えないような気がします。扶養手当・住居手当・通勤手当・期末・勤勉手当(ボーナス)が支給されます。
中学校教師の勤務時間と休日について知ろう
- 勤務時間はどのくらい?
- 土日の過ごし方は?
- 有給休暇は取れるの?
公立中学校の場合は、8時頃が勤務開始時間です。勤務の終了時間は16時から17時になっていますが、実際は2時間ほどの残業をする事が多いというのが現状です。部活動の指導、テストの準備、次の日の授業の準備、事務作業などがあり、勤務終了に帰宅できないことのほうが多いのです。
部活動などで生徒が学校にいる間は、生徒の安全や指導のために教師が先に帰るわけにはいきません。そのため、勤務時間は8時間を超えてしまうことが多くなります。また、休憩時間もほとんどなく、充分に休めていないというのが現状です。
中学校の部活は土日に練習や試合があることが多く、顧問をしている教師は部活に同行しなければなりません。平成18年に文部科学省で実施された「教育意識調査」によると、土日などの出勤が多いと答えた教師は48.0%にもなります。土日に休めていないという現状がアンケートからも分かります。
参考元:文部科学省 教員意識調査(全国の小・中学校の教員8,059人対象)
教師も継続勤務期間に応じて年次有給休暇が付与されます。しかし、実際はクラスの担当をしていたり授業の遅れなどを気にして休めない事が多いようです。夏休みなどの間で生徒が学校に来ない日などに有給休暇を取得するよう、校長先生や教頭先生が他の先生方に声をかけるなどして、教師に心身共にリフレッシュを促すことが必要なのではないでしょうか。
中学校教師には異動はあるの?
公立の中学校教師は市内での異動があります。同じ学校に何年赴任するか決まっていません。だいたい5年程度で異動ということが基本的に聞きますが、10年近く同じ学校で働く場合もありますし、5年たたずに異動する場合もあります。
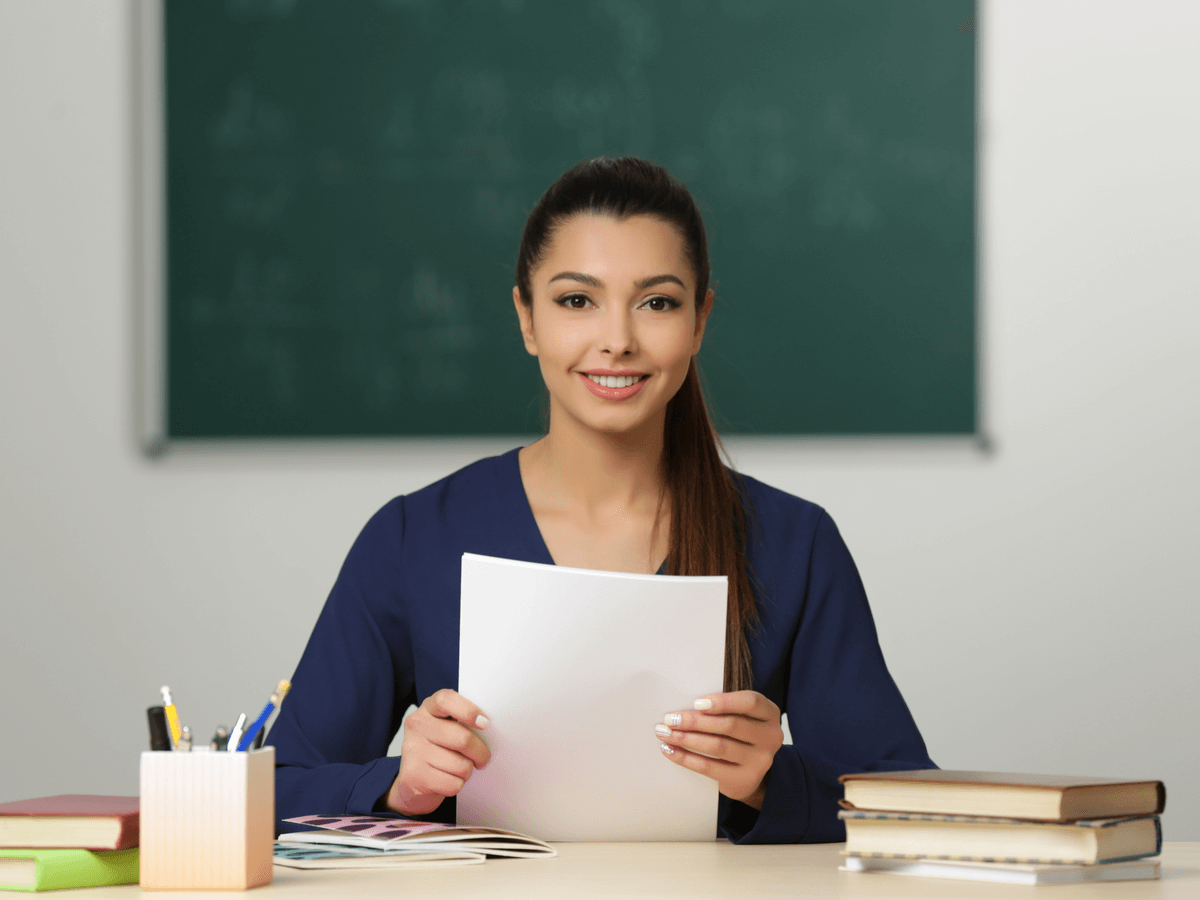
中学校教師になるのはどうしたらいいの?
短大・大学で教員免許状を取得する
中学校の教師になるためには「中学校教諭」と呼ばれる免許状を取らなければなければなりません。大学や短大で教職課程を修了すると、中学校教員免許を取ることができます。教員になるには教育大学に通学しなくても、教職課程という教員免許状を取得するために必要な授業が受けられる学校であれば取得できます。
中学校教師の免許には3種類があります。大学で取得できる「一種免許状」、短期大学で取得できる「二種免許状」、大学院で取得できる「専修免許状」の3種類です。最近では、一種免許状を取得する人が多くなっています。免許状の種類によって、教師としての仕事内容の違いはありません。
教員採用試験に合格する
大学や短大で教員免許を取得した後、教員採用試験を受けます。この試験に合格すると「教諭」として中学校で働くことになります。中学校教師の採用試験は非常に狭き門になっています。
中学校教員採用試験の難易度・合格率
中学校教師の採用試験は、約8倍の難関となっています。小学校教師の採用試験は4.3倍ほどなので、中学校教師のほうが難しいと分かります。日本では少子化の流れで今後、生徒がどんどん減っていくことが見込まれています。生徒が減るということは、教師も減るということになります。採用人数が少なくなる可能性もあることが予想されます。
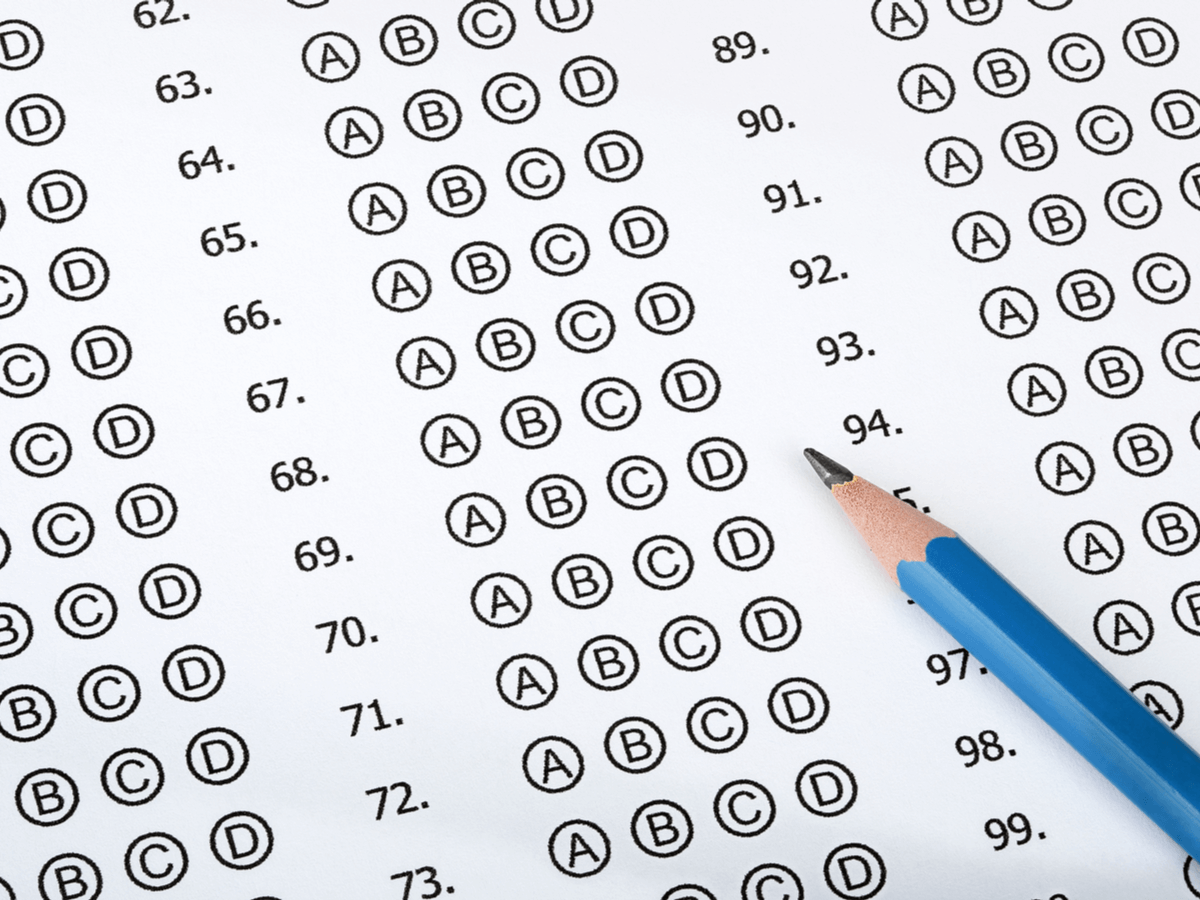
「臨時講師」と「非常勤講師」とは
中学校で臨時的に、または一時的に採用している「臨時講師」と「非常勤講師」という働き方で教師をしている人もいます。採用試験で合格できなくても講師として勤務するために登録しておけば、中学校で教壇に立つことができる場合があります。産休や育児休暇の代替の教員として働いたり、何かの事情で長期で休む教諭の代わりに、「臨時講師」として教壇に立てることがあります。「非常勤講師」は、常勤職員が務める1週間の勤務時間の4分の3を超えない範囲内で働かなければなりません。
「臨時講師」と「非常勤講師」をしながら採用試験にチャレンジして合格し、晴れて教諭になるという教師もいます。
中学校教師に向いている人
- 人に教えることが好きな人
- 割り切れる性格の人
- コミュニケーション能力が高い
教師なのですから、教えることが好きでなければ勤まりません。生徒たちに分かりやすく教えることができれば、生徒たちは学ぶことが楽しいと思えます。今までわからなかったことを知った時、分かった時の達成感を味わうことができれば、子ども達は「もっとできるようになりたい」と勉強への意欲を強くしていきます。
教えるのが好きでも自己満足であってはなりません。相手がどれだけ理解しているのか、把握できる人でなければなりません。クラスの中で大きな学力差が生じないようにするのも教師の腕の見せ所です。
残念ながら、中学校の教師で精神疾患による病気休職者は増加しています。(2015年文部科学省調べ)仕事の忙しさや生徒や保護者同僚との人間関係、教師の悩みは多く、真面目な人ほど真剣に悩んでしまいます。
子どもが好きで中学校の教師に夢を抱いていた人が、現実の厳しい毎日に挫折してしまうこともあります。学校での悩みを一日中考えてしまう人は、精神的に参ってしまいます。学校を出たら気持ちを切り替えて、家ではリラックスできるよう人が教師に向いているのではないでしょうか。
参考元:2015年文部科学省
中学校教師は生徒だけではなく、保護者や同僚とコミュニケーションをとることも仕事です。生徒の話を聞くためには、自分から話しかけて心を開かせるコミュニケーション能力が必要です。コミュニケーション能力とは「話が上手い人」というわけではありません。
人の話を聞くのが上手な人でも、コミュニケーション能力が高いといえます。相手がどんなことを伝えたいのか汲み取ることができる、無理やり話を聞かず相手のペースで話ができるなど、相手のことを考えた会話ができる人は教師に向いていると言えるでしょう。

中学校教師のやりがいと大変さとは
中学校教師のやりがい
- 生徒の成長が見られる
- 感動を分かち合える
- 生徒の人生の中に存在できる
中学校の3年間で子どもは大きく成長します。小学校を卒業したばかりの生徒が学校生活の中で、行事や部活などを通じて悩みを抱えたり壁に当たりながら成長していきます。内面も外見も見違えるように成長していく姿を、中学校教師はそばで見ることができます。1年生から3年生と続けて担任を持つことができた場合は、生徒たちと一緒に日々を過ごし卒業の時には感慨深いものを感じられることでしょう。
部活動では試合や練習、クラスでは文化祭や体育祭などの行事を生徒たちと一緒にやり遂げることで、生徒たちと感動を分かち合えることができます。一生懸命取り組んだからこそ、終わった時の達成感はひとしおです。
中学校の思い出は、大人になっても鮮明に残っているものです。自分が受け持った生徒から毎年のように年賀状をもらって、卒業後の様子を知れて「先生のおかげで英語が好きになって今度留学します。」などとの言葉をもらえた時は、教師をしていてよかったと思う瞬間でしょう。大人になっても忘れずにいてくれることはうれしいことです。

中学校教師の大変さ
- 忙しすぎる
- 生徒指導の難しさ
- 保護者との関わり
勤務時間のところでも触れましたが、中学校教師は授業だけでなく、部活動などで土日は休めずに、試合や練習に同行したりする場合があります。放課後も、授業の準備や試験の作成などをしたりして、毎日のように残業となることが多いのです。自分の時間や家族との時間が少なくなってしまう場合もあります。
中学生は思春期の真っ只中で、多感な時期です。教師に反抗して授業を放棄する、生徒同士のトラブルなど、対応に頭を悩ますこともあるでしょう。いじめや暴力が起きてしまい、生徒はもちろん保護者や時にはマスコミの対応をしなければならないことも出てきます。子どもは一人ひとり性格も感じ方も違いますので、対応もそれぞれ違います。それはいくらベテランの教師でも難しいのです。
近年、モンスターペアレントに学校が悩まされるということが問題になっています。保護者がクレームや無理な要望を言ってくることに対し、保護者の話を聞いて学校側の対応への理解や協力を得られるよう分かっていただくのは根気も時間も必要です。
中学校教師になるために必要なこととは
中学校の教師になるためには、心身共にタフなことが求められます。多忙な仕事をこなすための体力や、多感な生徒と向き合う精神力が必要です。そして、何よりも勉強を教えることが好きで、生徒と共に過ごす時間を楽しいと思えることが大切です。
働き方の改革が求められる中学校教師ですが、そんな中でも生徒の心にいつまでも残る先生が増えていくといいですね。

