日本が「フレックスタイム」という制度を取り入れるようになってだいぶ経ちますが、フレックスタイムとはどんな制度なのでしょうか。労働者のために取り入れる企業が多いですが、フレックスタイムのメリット・デメリットを含めこの制度について気になるところを詳しく解説していきます。
フレックスタイムという制度を知ろう

フレックスタイムとは
変形時間労働制のうちの一つである「フレックスタイム制」とは、労働者が自分で出勤・退勤の時間を決めることができる制度です。これは、1987年の労働基準法改正の時にできた制度で、労働基準法第32条3号に定められています。労働者は1日8時間で、1週間で最長40時間までの労働時間の中で出勤・退勤を決めます。自由度が高く、効率よく仕事が行えるとして、労働者の満足度を高めるためにフレックスタイムを取り入れる企業が増えてきています。
2種類の時間の定義
フレックスタイムという制度は、全てが自由だというわけではありません。業務に支障が出ないように、2つの出退勤についての時間が設定されています。
コアタイム
「コアタイム」とは、「必ず出勤していないといけない時間」ということです。このコアタイムが始まる時間に会社にいないと遅刻ということになり、時間内に帰宅すると早退扱いになります。フレックスタイム制の中にコアタイムを設けないと、社内での打ち合わせなどに支障をきたすことがあります。
フレックスタイム制を導入している企業の多くは、このコアタイムも同時に取り入れています。
フレキシブルタイム
必ず会社にいないといけない時間であるコアタイムの前後に設ける時間のことを、「フレキシブルタイム」といいます。コアタイムの前と後ろに設けるのがフレキシブルタイムで、この時間内であれば、何時に出勤しても退勤してもいいことになっているのです。
労働時間の管理方法
フレックスタイムというのは、日によって労働時間が変わることがあり、そのため日ごとに1日の労働時間が違うことがあります。そのため、週ごとまたは月ごとに労働時間を設定します。この設定時間を「清算期間」と呼びます。清算期間は、法定労働時間内に収まる時間内であれば、企業が独自に設定することが可能です。
清算期間の総労働時間を、通常の定時というようにして考えます。法定労働時間とは、「1日8時間以内・1週間40時間」と定められている労働時間のことです。ですから、フレックスタイムを導入している会社は、この範囲内で総労働時間を月に何時間以内、週に40時間との設定をする必要があります。
フレックスタイム制の精算時間の計算式は以下の通りです。
総労働時間 ≦精算期間(日数)÷7日×40時間
引用:厚生労働省 東京労働局

フレックスタイム制の残業の扱いについて
フレックスタイム制で働く時、残業の扱いはどうなるのでしょうか。労働者が自由に出退勤を決められるフレックスタイム制では、残業時間の数え方も少し特殊です。勤務体制が通常である場合は、1日8時間の固定時間以上の労働があると残業時間として賃金が割増になります。
フレックスタイム制で働いている場合は、1日8時間以上働いた時でも、あらかじめ定めた一定時間(週に40時間など)を超えたときが残業時間となります。また、フレックス制の導入が労使協定により決まっている場合、36協定や変形労働制を導入しなくても、1日8時間以上の労働も労働基準法の違反にはなりません。
以下は2点は、残業についての考え方です。
法内超勤
労働時間が1日8時間以内の場合の残業のことです。9~16時までの7時間勤務の人が、1時間残業をしたとします。この場合は、法律で定められている1日8時間以内の労働になるため、残業とは捉えられません。この労働者に会社側が8時間分の給与を通常通り支払います。
時間外労働
法律で決められた1日8時間を超えて残業した場合は、8時間を超えた時間分について時間外労働となります。時間外労働の場合、会社は通常通りではなく割増の賃金を支払う必要があります。
残業代については、企業の就業規則などで定めがある場合がありますが、労働基準法で決まっている「8時間を超える残業の場合は25%増し」「22時から5時までの深夜残業の場合は50%増し」「休日労働の場合は35%増し」を下回っている場合は、労働基準法違反です。
18歳未満にはフレックス制を導入してはいけない
フレックスタイム制を18歳未満の年少者には導入することができません。これは労働基準法第60条で定められています。
フレックスタイム制でも休憩時間を設ける必要がある
フレックスタイム制でも、休憩時間を設ける必要があります。だいたいの企業は休憩時間は全従業員が一斉に取るため、コアタイムの中に設定しています。しかし、別途労使協定を締結すれば、休憩時間に関しても労働者が自由に決めることができるのです。

フレックスタイムを採用するための要件
労使協定との締結をする
フレックスタイム制を取り入れる場合には、労使協定を締結しなければなりません。このことは労働基準法に書かれています。労使間で合意があったとしても、労使協定を締結していない場合は、フレックスタイム制の導入はできないのです。そして、以下の内容を労使協定で定めなければなりません。
フレックスタイムの対象となる労働者とは?
会社内でフレックスタイム制を導入する場合には、その対象になる労働者の範囲を定めることが必要です。範囲は全従業員でもいいですし、各人ごと、グループごとなどでもいいのです。必ずしも会社全体で取り入れる必要はありません。労使で話し合いをして協定で明確にします。
清算期間
清算期間というのは一般的には賃金の計算期間に合わせ、1ヶ月とする場合がほとんどです。フレックスタイム制の中で、労働者が働くべき時間を定める期間のことを指します。
清算期間における決算日
決算日は、毎月1日や16日などのように、清算がどの期間であるかをはっきりと分かるようにしなければなりません。単に「1ヶ月」とはしないようにします。
清算期間におけるすべての労働時間
これは、フレックスタイム制における労働契約上で、清算期間内に労働者が働かなければいけない時間を設けたものです。これは所定労働時間のことを指します。清算期間を平均し、労働者の1週間における労働時間が40時間以内に収まるように定めなければなりません。
※「特殊措置」という週の法定労働が、40時間以上になるものがあります。一部の業種ではこの場合、週の法定労働時間が44時間になります。対象になるのは以下の業種で、いつも労働者が10人未満である事業場です。そして、清算期間の総労働時間の計算は、40時間を44時間にして計算します。
| 商業 | 不動産管理・卸売・小売・出版 |
|---|---|
| 映画・演劇業 | 演劇の興行・映画の映写など |
| 保険・衛生業 | 保育園・老人ホーム・病院・診療所などの社会福祉施設 |
| 接客・娯楽業 | 遊園地・旅館・理美容院・飲食店など |
就業規則に定める
フレックスタイム制を取り入れるためには、適用を就業規則等に定めてこのことを労働者に知らせることが必要です。「フレックスタイム制を導入した」ということを従業員に知らせれば、全ての内容を従業員に把握させなければならない、ということはありません。従業員が自信で内容を調べることができる状態であればいいからです。
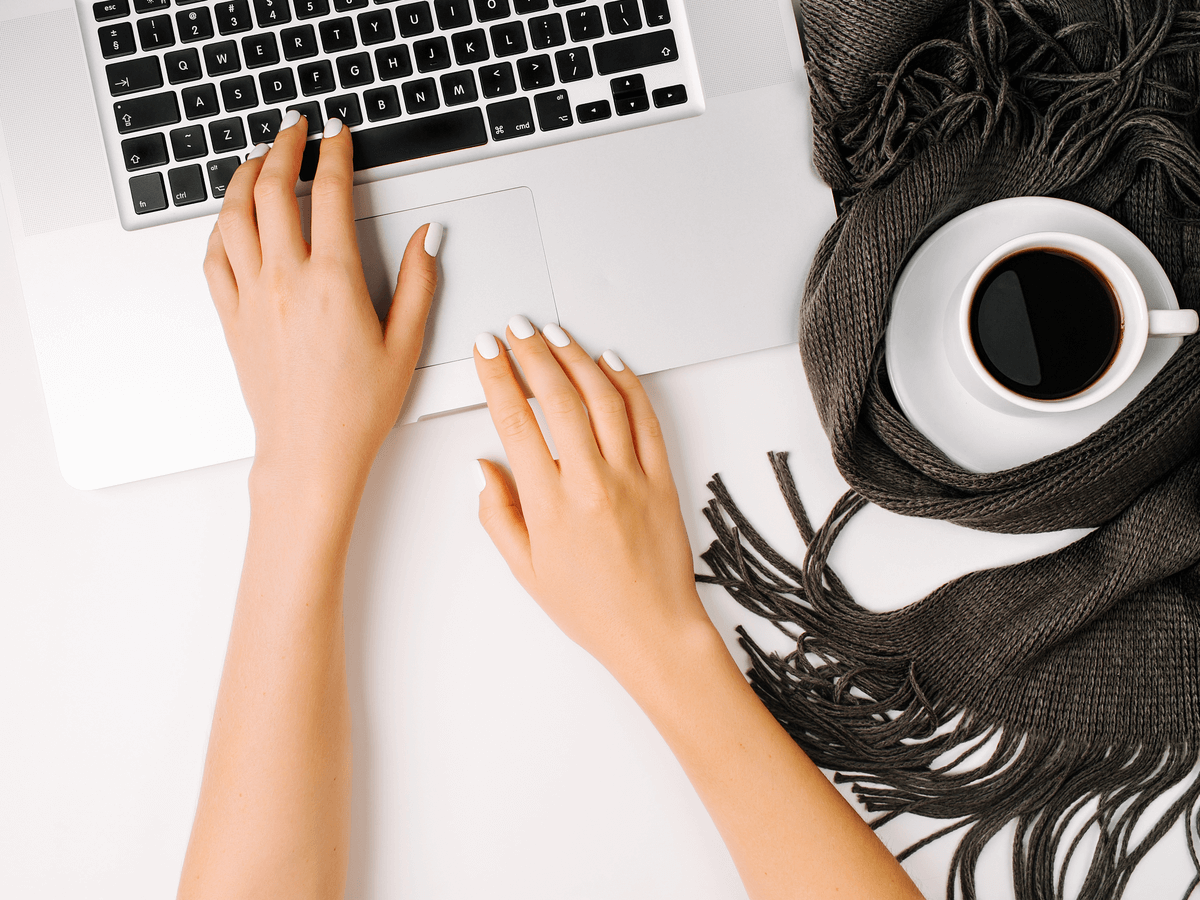
フレックスタイムの導入状況
実際にフレックスタイムを導入している企業は、どのくらいあるのでしょうか。厚生労働省が行なった「就労条件総合調査」(平成28年度)を参考に見ていきます。
調査によると、変形労働時間制(フレックスタイム制)を採用している企業は全体の60.5%です。半数以上の企業が、フレックスタイム制を導入していることがわかります。企業規模別で見てみると、1,000人以上がフレックスタイム制を希望しているおり、その比率70.7%で最も多く、300~999人が67.2%、100~299人が64.0%、30~99人が58.5%でした。
産業別に見てみると、最も多い割合でフレックスタイム制を導入しているのは、「鉱業・採石業・砂利採取業」で79.9%でした。フレックスタイム制導入の一番少ない産業は、「金融業・保険業」で26.9%でした。
この結果から、労働者の人数が多いほどフレックスタイム制を導入している企業が多いのが分かります。また、業種別では導入しづらい業種もあるのが現状なのではないでしょうか。接客業の場合は、お客様の対応をするための時間が限られているということもあります。全ての業種がフレックスタイム制を導入できるということではなさそうです。

フレックスタイムのメリット
プライベートを充実させることができる
フレックスタイム制を導入することで、プライベートを充実させることができるという利点があります。時間の決め方で、自身の生活リズムに合わせて出退勤ができます。例えば子育てをしながら仕事をしている人の場合、朝に子どもを保育園に預けるために慌ただしい時間を過ごすことなく、ゆっくり出勤することができます。
子どもが大きくなり、小学生や中学生になったら朝早めに出勤し、帰宅を早めて子どもの宿題を見てあげるなど、子どもとの時間が作れます。また、時間の使い方によっては、趣味や資格の取得のための勉強をすることができます。このようにフレックスタイム制は、自分だけではなく家族にとってもよい制度だと言えるでしょう。
効率的に時間を使い残業が減る
フレックスタイムは1日8時間の労働ですが、時期によって出退勤時間を変更することができます。繁忙期には取引先に合わせて9時から18時の勤務にする、閑散期は自由に時間を変更するなども可能です。また、時間の使い方によっては無駄な残業が防げることもあります。
通常時間で仕事をしていた場合、仕事が終わりそうもないけど1時間くらい残業していけばいいやと思うことがあるかもしれません。しかし、例えば10時から19時の勤務で仕事をしている場合、残業をしたら帰宅時間が遅くなってしまうため、集中して仕事を終わらせようとする意識が働きます。
通勤ラッシュのストレスから逃れられる
毎日の通勤は、かなりのストレスがあります。満員電車に乗って通勤することで、会社に着く頃にはすでに疲れてしまっているという場合もあるでしょう。フレックスタイム制を使った場合、朝の通勤ラッシュの時間を避けて電車に乗るなどできるので、ストレスを軽減して仕事に向かうことができるというメリットがあります。
自主性を大事にするので意欲が高まる
フレックスタイムは自分で労働時間を決めることができるので、労働者の自主性が生まれます。自分で考えて行動するという意識で仕事ができるため、仕事に対する意欲も高まるのです。

フレックスタイムのデメリット
従業員同士のコミュニケーションが減る
フレックスタイムを使うと、同じ会社内でも違った時間に出勤してきて、帰る時間もまちまちだということがあります。そうなった場合、社内でのコミュニケーションが減ってしまうことがあるかもしれません。話す時間が少ないからメールで済ませようとするなど、顔を見ての会話が減ってしまう可能性が大いにあります。
そういった場合、急な社内会議などを行う時に、支障がないようコアタイムを導入している企業が多いのです。
電気代などの経費がかさむ
フレックスタイム制を導入している会社は、それぞれが自身が決めた時間で仕事をするので、従業員が会社にいる時間が長くなります。そのため、電気代や水道料金などの社内の経費が余計にかかることになります。

フレックスタイムを有効に使おう
フレックスタイムは、労働者によっては嬉しい制度と言えるでしょう。満員電車を避けて出勤することができ、自身の自主性を尊重してくれる制度でもあるからです。この制度を導入する場合は、仕事の効率を考えた導入でなければなりません。ただ単に、「早起きが苦手だから朝遅く出勤しよう」という考えは少し違うのかもしれません。
朝の通勤ラッシュを避けてストレスを減少させる手出勤することで、効率の良い仕事ができるなどの理由があってこそのフレックスタイムです。フレックスタイムを導入する場合は、会社側も従業員側もそのメリット・デメリットを充分に理解した上で取り入れていくことがいいのではないでしょうか。

